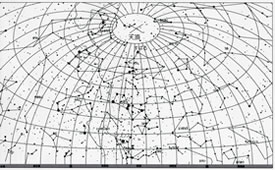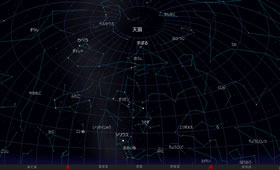| 第41回
オリオン座のベテルギウス
12月はイルミネーションが美しい
|
12月になると夜は、空よりも地上の光の方に注目されるのがこの頃で、それは、クリスマスシーズンのイルミネーションですが、つくばでは、100本のクリスマスをはじめ、つくばセンター付近のけやきのイルミネーション、それに各地のショッピングセンターや個人のお宅でもイルミネーションを輝かせているところが多く見られるようになりました。
星見を愛好する人々にとってイルミネーションは大敵?とも考えられますが、星見の仲間たちも生活が全て星見で埋め尽くされているわけではありませんし、光から感じられる暖かさは、心をいやしてくれる効果も大きく、決してイルミネーションを否定するものではありません。
|

100本のクリスマスツリーの夜景
写真は過去の100本のクリスマスツリーの様子。今年はどんなすてきなツリーが見られるか楽しみですね。12月9日に点灯式が行なわれ、クリスマスまでの期間、TXつくばエクスプレスつくば駅に至近のつくばセンター広場で行なわれます。
|

物質・材料研究機構のイルミネーション
つくば市千現にある独立行政法人物質・材料研究機構のイルミネーション(タテ16メートルヨコ8メートル)は、数々の物語を生んできましたが、今年はどのような図案でしょうか。楽しみですね。 |
さまざまな工夫をこらしたイルミネーションを見るとき、むしろ感激とか感動といったことばが出てきますし、その美しさは、イルミネーション自身が「見て見て!」と私たちギャラリーに見てもらうことで喜びを感じているかのようにもとらえられます。
省エネに反するとか植物に悪い影響があるとか、さまざまな見方があり、それを否定はしませんが、そうしたことを差し引いても、心を和ませてくれる美しさや感動は、豊かな文化のひとつととらえることができ、私は大好きです。 |
| では、イルミネーションがあっても星見はできるのか、じゃまにはならないのかといった意見もありそうですが、光害(ひかりがい)全般でいえば、星見の大敵はイルミネーションよりも、足下や地面を主に照らせばいいはずの街灯が空や街路樹の高木の枝葉まで照らしたり、あるいは空に照射される回転サーチライト(つくば付近では最近見かけませんが・・・)といったものの方がよほど夜空の星を見えにくくしているのです。
この季節に星見をするときは、直接イルミネーションや街灯の光が眼に入らないところで暗さに眼をなじませて星空を見上げるようにしましょう。もちろんお子さんの場合はおひとりではあぶないですから、ご家族同伴で安心して星見を楽しんでください。
イルミネーションも星見もぜひ、両方を楽しんでいただきたいと思います。
|

光のページェント
杜の都仙台では300万人が訪れるSENDAI光のページェントと称するイルミネーションを市内の定禅寺通、青葉通で行ないます。今年は12月12日から大晦日まで221本のけやきに70万個の電球が点灯します。 |
12月の星座案内(おうし座)
|

すばるの写真
|
冬の到来を告げる星空というと、私はおうし座をあげます。
おうし座には有名な星団「すばる」があり、この季節になると夕闇が迫りくる頃、東から昇ってくる姿がとても印象的で、木枯らしによって落葉した木立の向こう側から昇りくる様は、冬の到来を告げているように感じられます。
すばる(星団)を先頭に、続いてアルデバラン(一等星)を含むヒアデス星団も昇ってきておうし座の全容が見えてくると、「ああ、冬の到来だ」と実感してしまうのです。
すばるについて少し詳しく説明することとしましょう。すばるは肉眼で見ると、羽子板のような形に6個の星が集まった星団のように見えます。これを双眼鏡などで見てみると30個以上の星の集団に見え、さらに天体望遠鏡を使えば100個以上の星の集団であることがわかります。写真では星々にはベールのような淡い星雲が取り巻いている様子が確認できます。
|
「すばる」ということばは日本の古い古語で、清少納言の枕草子にも登場します。すばるは、地方によって様々な呼び名があり、その一部を紹介すると、むつらぼし、ろくじぞう、すまる、すばり、はごいたぼし、むじなぼしなどがあります。昔から人々に知られ、親しまれてきた様子が呼び名からもうかがえます。
西洋では7人姉妹にたとえられ、プレアデス星団と呼ばれていました。
日本では6個、西洋では7個に見えたこの星団、約120個くらいの誕生してまだ若い青白い星々で構成されています。
この美しい星の集団と星座は話題の種にもなります。ぜひ、みつけてみてください。
12月の星座案内図
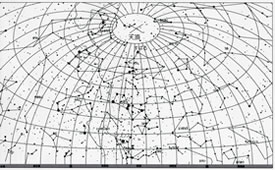
白地星図 |
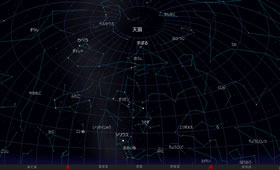
黒地星図 |
|
※それぞれの図をクリックすると、大きい星図に変わります。印刷される場合は、A4用紙を横にしてください。
※この星図は、株式会社アストロアーツの天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータVer.7」から出力し、加工したものを使用しています。
|
双眼鏡がほしい
冬を迎え、星見やバードウオッチング用に双眼鏡がほしいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
そこで、今月から数回、双眼鏡の性能や購入のアドバイスをいたします。
双眼鏡はメーカーや種類が多く、しかも価格もピンからキリまであって、性能の差もあり、どういったものが星見に適しているか見当がつきませんね。お店も眼鏡店、カメラ店、玩具屋、ディスカウントショップなどあらゆるところで販売されています。
そこで、どのような基準で選ぶのか、双眼鏡の特性や購入までの検討プロセスをご紹介していきたいと思います。
まず、今月は、双眼鏡の性能にかかる表示と天体用に向く倍率と口径(対物レンズの直径)についてご説明します。
12×25の意味は?
双眼鏡には本体に、12×25といった数字の表示があります。
この12×25というのは何でしょうか?単純に計算してしまうと(12×25=300)となり、300倍の倍率なの?と思ってしまうかもしれませんね。正解は、像の拡大率を示す倍率は12倍で対物レンズの口径(直径)が25ミリあるという意味なのです。
また、写真で示していますが、胴体がまっすぐなのがダハプリズムなどで像を成立にするタイプ。胴体が折れ曲がっているような形がポロプリズムタイプと呼ばれる伝統的なスタイルの双眼鏡です。
倍率は高い方がいいか?
| 通常の手持ち双眼鏡では、倍率は低い方が見る対象がブレずに安定して見ることができます。倍率が高いと大きく見えても対象がブレますので、ゆらゆら揺れているように見え、対象をはっきりと見ることができません。
倍率は6倍から10倍程度ではあまりブレは感じませんが、12倍とか20倍という双眼鏡では三脚などに固定しないと対象を鮮明に見ることができません。
天体観察用に用いる双眼鏡では、手持ちで観察することを前提にすると倍率は7〜10倍、口径は40〜50ミリ程度が適しています。このクラスの中では私は7×50(7倍50ミリ)を使用しています。 |

双眼鏡
天体観測に人気のある機種は7×50(写真右)のちょっと大きめな双眼鏡です
|
三脚に固定する場合は、倍率15〜20倍、口径70〜80ミリ程度のものが持ち運びの利便さも考慮すると適しているといえます。私は16×70を使用しています。三脚はカメラ用のものを流用しています。
一般にバードウオッチングなどに用いる双眼鏡は、口径が20〜40ミリ程度のものが多く、天体用には口径がちょっと物足りなく、星や星雲などを探すのには、口径が大きい方が光を集める能力(集光力といいます)が高いので、大口径の方が天体向きの双眼鏡といえるのです。
次回も双眼鏡のアドバイスがあります。お楽しみに。
2006年12月5日
|