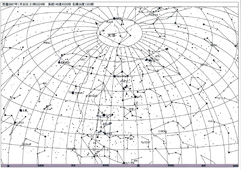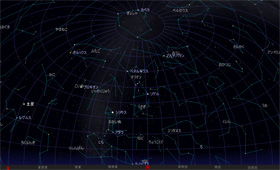| 第42回
オリオン座のベテルギウス
オリオン座とベテルギウス
|
冬の星座の代表といえばオリオン座です。畏怖堂々としたオリオンの姿が浮かび上がって見えてくるような星の立派な配列が、星空を見上げる私たちに感動を与えてくれます。
三つ星の輝きやオリオン座の1等星ベテルギウスとリゲルの紅白の色の違いなどは見ていて星の不思議さも感じさせてくれます。
そのオリオン座で昨年は、1等星ベテルギウスに注目が集まりました。
なぜ、注目を集めたかというと、ベテルギウスの明るさ(光度)が変わり、暗くなってしまったのです。
永久に不滅のように感じる恒星の明るさですが、実は私たちの太陽をはじめ、夜空に輝くたくさんの恒星たちには明るさに変動があるものが少なくありません。
話をベテルギウスに戻しますと、通常は0.45等の明るさを保っているのですが、昨年秋には1.2等星まで暗くなり、同じオリオン座の1等星リゲル(0.18等)と比較すると明らかに暗く見えたのでした。 |

オリオン座の写真
オリオン座は真ん中に3個の星が並んだ三つ星のある有名な星座で、ほかの星座はわからなくてもオリオン座だけは知っていると、人々にいわせるほど親しまれています。星の明るさを比較したり、星雲を探したりといった天体観測の入門の対象として親しまれています。 |

オリオン座の星座絵
星座の星々に付けられた固有名を表示しました。ベテルギウス、リゲル、ベラトリックスといった恒星名のほか、オリオン大星雲の位置も覚え、この図を参考にしながら、実際の星雲を双眼鏡などで確かめてみてください。 |
どうしてこうなったのでしょうか。この原因はベテルギウスが、星の一生の中で晩年を迎え、現在は赤色巨星(せきしょくきょせい)と呼ばれる大きな星となっているからなのですが、ベテルギウスの直径は太陽の約1,000倍という超巨大なサイズまで大きくなり、不安定な状態が続いて、ちぢんだりふくらんだりしているのです。
その結果から、明るさが変わって見えるので、脈動変光星と呼ばれています。
ふくらんで明るく見えるときは、0.45等まで明るくなり、こいぬ座のプロキオン(0.40等)とほぼ同等なのですが、最も暗く見えるときは、ふたご座のポルックス(1.16等)に近いくらいまで暗くなってしまうのです。
双眼鏡を使って、星同士の明るさの比較なども楽しい観測で、変光星観測と呼ばれています。もちろん、双眼鏡を使えば、有名なオリオン大星雲も見ることができます。 |
1月の星座案内(冬の星座)
晴天で月明かりのない夜に星空を見上げるとこの時期は冬の星座で空は一面覆われています。今月は、10日から25日ころにかけての空では月明かりの影響も少なく星座をはっきりと見て、確認できることでしょう。
冬の星座の1等星の名前は、全部知っていますか?
冬は1等星がもっとも多く、7つあります。ぎょしゃ座のカペラ、おうし座のアルデバラン、オリオン座のベテルギウスとリゲル、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオンそしてふたご座のカストルです。
ベテルギウスを除く6個の1等星を結ぶとできる6角形は、空に壮大な6角形が見られ、みつけると同時に星座も覚えられますので、寒さにじっと耐えて、確認しましょう。
偏西風のおかげでキラキラと輝き、瞬く冬の星々は、きっとあなたに寒さをわすれさせて星の美しさを提供してくれることでしょう。
1月の星座案内図
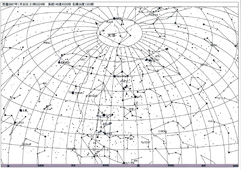
白地星図 |
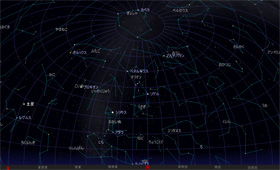
黒地星図 |
|
※それぞれの図をクリックすると、大きい星図に変わります。印刷される場合は、A4用紙を横にしてください。
※この星図は、株式会社アストロアーツの天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータVer.7」から出力し、加工したものを使用しています。
|
双眼鏡がほしい(シリーズ2)
双眼鏡がほしいシリーズは今月で2回目になりますが、「天体がはたして双眼鏡で見られるのか、天体望遠鏡でなくてはだめなのではないか」といった疑問にお答えするために今月は、双眼鏡の光学的能力などについて述べます。
暗い星まで見る
天体望遠鏡や双眼鏡で見ることのできる星は、肉眼で見ることができる星の等級よりも暗いものまで見られることは容易に想像がつきますが、では、どの程度、暗い等級の星まで見ることができるのでしょうか?
私たちが肉眼で星を見るときは、眼の瞳が最大まで開いても瞳の直径は7ミリメートルといわれています。天体望遠鏡や双眼鏡では対物レンズの口径(直径)が大きく、たとえば口径5センチの双眼鏡では、直径が50ミリメートルですから光を集める能力は、人間の眼に対して、次の式で表されます。
集光力=対物レンズの口径の二乗÷人間の瞳径の最大値(7mmの二乗)
(50×50)÷(7×7)=約51
したがって集光力は51倍となります。
この集光力の数字が大きいほど暗い星を見る能力があり、見える限界の等級が伸びます。
次の表で、各口径ごとの集光力と極限等級を確認してください。
口径ごとの集光力と極限等級
| 口 径 |
集光力(倍) |
極限等級(等) |
| 30 |
18 |
9.2 |
| 40 |
33 |
9.8 |
| 50 |
51 |
10.3 |
| 60 |
73 |
10.7 |
| 70 |
100 |
11 |
| 80 |
131 |
11.3 |
| 100 |
204 |
11.8 |
星雲を明るく見る
星雲や景色を見るときに、同じ口径の双眼鏡でも倍率が低い双眼鏡の方が明るく見えることは、実際にいくつかの双眼鏡を使うと経験的にわかります。
星雲、星団ウオッチングでは、当然のことながら明るく見える双眼鏡の方がいいわけです。瞳の中に大きな光の束で入ってくるためには、同じ口径ならば倍率が低い方がいいのです。
この明るさの度合いは、双眼鏡のカタログなどを見ると、単に「明るさ」といった表示で数値が表現されていますが、正式には「光明度」といい、口径は大きいほど、また、倍率が低いほど光明度は高くなります。
計算式は次のようになります。 光明度=口径の二乗÷倍率の二乗
したがって、10×25(倍率10倍で対物レンズの口径が25ミリ)の双眼鏡では
(25×25)÷(10×10)=6.25
明るさ(光明度)は、約6となります。
次に、7×50(7倍50ミリ)ではどうなるでしょうか。
(50×50)÷(7×7)=51.02
明るさは、約51となります。
この数値が昼間に使用する双眼鏡では、6〜20程度でも明るく見えますが、夕方とか森林の中では25前後は必要になってきます。そして、夜間使用では50前後のものが用いられてきました。
では、天体観測用では、どの程度の数値が必要でしょうか?
見やすさからすると、50が優れていますが、だいたい25〜50くらいのものが実際には使用されているようです。これから双眼鏡をお買い求めの際の参考にしてください。
三脚に固定して見る
| 先月の説明の中に三脚に固定して見るときは双眼鏡固定金具で三脚に取り付けると説明しましたが、ちょっとわかりにくかったようなので、今月は写真で見ていただきたいと思います。この金具は、双眼鏡アダプターとかビノホルダーといった名称で販売されていて、1500円〜3000円程度で買えますが、ご自分の双眼鏡にあった金具をお求めにならないと、取り付けられませんのでご注意ください。
三脚に付ける利点は、視野が揺れないだけでなく、ご自分でみつけた対象を他の人にも見てもらえる利点があります。手持ちで見ても、他の方には同じ視野は見せられませんが、三脚で固定されていると、交代して視野を覗くことができます。
ぜひ、ご家族や友人たちと、冬の星雲星団(オリオン星雲やすばるなど)のスターウオッチングを双眼鏡で楽しんでください。
|

取付金具付き双眼鏡
とらえた星雲などを家族や友人に見てもらうためには、この写真のように双眼鏡を三脚に固定する金具がないと視野が動いてしまい、せっかくとらえた天体が視野からはずれてしまいます。双眼鏡を買い求めるときにはぜひこの金具もお買い求めください。 |
2006年1月9日
|